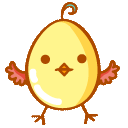
丸山真男が一兵卒として体験した戦争は、一言でいえば知識人として「普遍的な」意味を持つ体験であった。才能ある丸山は、それを自覚的に、また思想的に体験した。敗戦前に彼がすでに戦後日本の「民主主義」を先取りしていたことは、彼の俊敏さとともに、それが「進歩的」知識人として「普遍的な」体験であったことを物語っている。実践される前に「先取り」されたがゆえに丸山の「民主主義」は、戦後大衆が奪取すべき民主主義とはかい離したものとなる徴候をはらんでいたともいえる。
・・・・・私(吉本)が丸山の敗戦までのイメージをよくつかめなかったのは、ほとんどその思想が大衆の生活思想に、ひと鍬も打ちいれる働きを持っていなかったことを意味している。
リベラルな日本知識人の多くはアタマのなかで考えあぐねていた。
「敗戦で打ちのめされた日本の大衆は、支配層の敗残を目の当たりにし、食物も家もなくなった状態で、何をするだろうか?
暴動によって支配層を打ちのめして、みずからの力で立つだろうか?
あるいは徹底抗戦をゲリラ的に進めて、「終戦」をほんとうの「敗戦」に持っていくだろうか?」・・・・と。
しかし日本の大衆はなにもしなかった。
大衆は天皇の「終戦」詔勅をうなだれて聞き、無抵抗に武装を解除して、荒れ果てた故郷に帰っていくだけであった。
わたしたちはこのとき絶望的な大衆のイメージを見たのだが、丸山に言わせれば、「解放された御殿女中とはこういうものであった」。
・・・・・残念なことに丸山真男の戦後の思想からは解放された御殿女中のその後を聞くことができない。
吉本隆明 『丸山真男論』(ちくま学芸文庫)1/2 - 週に一冊
http://oshimayukinori.hate
nablog.com/entry
/20150112/1421027205
※前スレ
吉本隆明「暴動により支配層を打ちのめす事もせず、天皇の『終戦』詔勅をうなだれて聞く大衆に絶望のイメージを見た」 [511393199]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1606653597/

