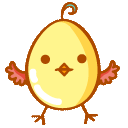
ビジネスの現場で「ナラティブ」というキーワードが注目されつつあります。ナラティブとは、人びとが自分自身の体験から紡ぎだす言葉(物語)であり、語る人と聞く人がともに創り出す物語ともいえるもの。では、なぜ企業のコミュニケーションにナラティブが求められるのでしょうか。マスメディアを通じた発信に慣れたマーケターにはしっくり来ないかもしれません。
本稿では、書籍『ナラティブカンパニー 企業を変革する「物語」の力』の著者でPRストラテジストの本田哲也氏と、マーケティングや広告・メディア事業のコンサルタントで社会構想大学院大学特任教授として教壇にも立つ高広伯彦氏が、2回にわたって「ナラティブ」をテーマに語り尽くしました。話題は社会学から哲学、人気アニメ、パーパス、と縦横無尽に広がって……。
ナラティブには語り手の人生が表れる
本田:『ナラティブカンパニー』の刊行がおよそ1年前のことですが、ここ最近マーケティングやブランディングの文脈で「ナラティブ」が話題に上ることが増えていると感じます。ナラティブ(narrative)は「物語」とか「語り」と訳されますが、一方で色んな解釈がされやすい言葉でもあります。
注目されつつある今だからこそ、改めてナラティブの本質について高広さんと掘り下げていきたいと考えています。
ナラティブという言葉は1990年代ごろから出てきていますが、当初は主に医療や教育の分野で使われてきました。ビジネスの世界で注目されてきたのはここ4~5年のことではないでしょうか。行動経済学の権威でノーベル賞受賞のロバート・シラー先生(イェール大学教授)による『ナラティブ経済学』(2019年)はその契機のひとつと思います。
高広:今回の主旨を聞いて、ナラティブに関連する書籍を持ってきました。
高広:まず「ナラティブ」は身体性を伴うもの。書き言葉との対比でいうと話し言葉の側にある概念といえます。
本田:やまだようこ先生(心理学者・京都大学名誉教授)の『ナラティヴ研究』でも指摘されていますね。語られた内容を、語りの要素を残しながら再構築するのがナラティブ。語りの身体性が重視されるのは経験や考え方など、語り手の人生が表れるからでしょうね。
大きな物語の時代が終わり、無数のナラティブが生まれた | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議
https://www.google.com/amp/s/www.advertimes.com/20220526/article384710/amp/

